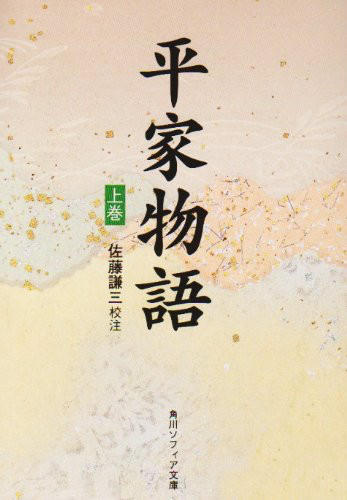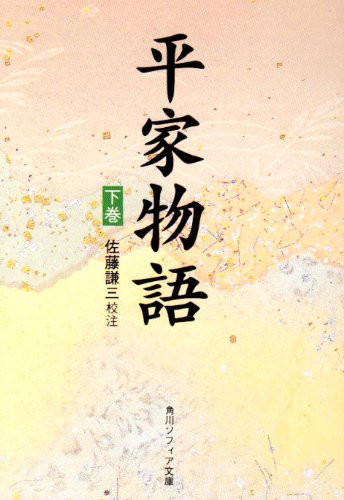面白いもので,藝技,遊女,いまで言えば,芸能人というのは,昔から,どんなに出自が卑しかろうと,藝や容色において優れていると,権力者の周辺に招かれ,権力者その人から直接の庇護・援助を得られ,権力に食い込むことが出来る。日本史において,これは武家・世俗政権のみならず,皇室権力についても同様である。アソビ女は,階級・貧富を超え,上下貴賤を往来できる特別な存在だった。
平安末期,後白河院が,娼婦に近い生業を生きていただろう白拍子や傀儡女を邸に招き入れて,今様の研究に没頭し,その成果を『梁塵秘抄』として遺したことはよく知られている。鎌倉時代に成立したとされる『平家物語』にも,『妓王の事』という,平清盛に愛された白拍子・妓王のエピソードがある。

『平家物語』角川文庫版
仏御前は,当世めでたき入道平清盛に己の白拍子の藝を売り込みもうと清盛の邸に押しかけるも,当然アポなしでは面会も叶わず,門前払いを食らう。平清盛の愛人・妓王は,かつての自分と同じ白拍子である仏御前を憐れみ,清盛に仏御前の藝を観るよう進言する。妓王の望みとあらばと,清盛は仏御前を招き入れ,その今様を聴き,舞を観る。清盛はたちまち彼女の藝と色香の虜となり,仏御前を半ば無理矢理に愛人として迎え入れ,この上は妓王を冷たく追い出してしまう。
妓王は次の歌を遺して,最高の権力者に疎まれた上は,母,妹とともに出家する。
この仕打ちに妓王を憐れんだ仏御前も,妓王を追って己自身も出家してしまう。萌え出づるも枯るゝも同じ,という同様の思いからだろう。
『平家物語』は,よく言われるように,「祇園精舎の鐘の声,諸行無常の響あり」の冒頭が象徴する,栄える者は必ず衰えるという末世の世界観が全編に通底している。語り手は,その客観的な語りの立場を逸脱して,仏法の末世を嘆き,滅びゆく者を憐れむ。『妓王の事』は,このコンテクストにおいて,愛される美女もいずれは飽きられ捨てられるという,諸行無常,盛者必衰のモチーフの変奏といえる。
平安貴族・武家・寺社の政争と戦乱の一大叙事詩に,かくして藝能の女性のエピソードが細やかに挿入されている点は,語りの題材の幅の広さのみならず,日本のアソビの伝統における遊び女(藝技,遊女)と権力との関わりをも象徴的に表しているようで,『平家物語』の極めて興味深いところである。