今日,2 月 11 日は紀元節。皇紀二千六百七十四年である。ダンテ・アリギエーリ『神曲 Divina Commedia』についてもう少し。紀元節とはまったくもって無関係なのだが。
“Divina Commedia ” はもともとただ単に “Commedia ” 喜曲という名だったらしい。地獄の暗澹たる絵ではじまり天に上る幸福感で結末を迎えるという意味で,終わりよければの古典的命名としての「喜劇」。それでも現代に生きるわれわれからすれば,この世の書かれた人間的ドラマは,どんなに悲惨であろうとも,全知全能の神にとっては喜劇のようなもの。そういう諧謔的ニュアンスで捉えてしまうところもあろうか?
先日は,村松真理子著『謎と暗号で読み解く ダンテ「神曲」』を読んで,入門書という位置づけの書籍に対して,大人げのない不必要な毒づきをしてしまった。ダンテ『神曲』への思い入れが,どうも著者と私とでまったく違う方法を向いているような気がしたからかも知れない。
「ここを過ぎて悲しみの市(まち)」とは太宰治の短編『道化の華』の書き出しで,これは『神曲』地獄篇第三曲の冒頭にある地獄の門の銘のひとつからの引用である。学生のころから熱心に読んで来たプーシキンにも,ダンテからの引用が数多く読み取れる。学生時代の私もその背景を「勉強」しなければならないと思い,岩波文庫の古色蒼然とした山川丙三郎訳『神曲』を手に取った。なんとか読み通した。でも,ほとんど心に響いて来なかった。
その後,就職して十年間は電子計算機にこき使われ,労働基準法などおかまいなしの労働地獄に落とされ,身も心も削った。「文学」なんて贅沢の出来ない精神状態を突っ走り,読まなければならないのは大型コンピュータや,UNIX,ネットワーク通信の技術書,システム工学書ばかりだった。ロシア語もフランス語もギリシア語も頭っからスパーと抜け去って,代わりにアセンブラ,C/C++,PL/I などのコンピュータ言語や金の計算で頭を占有されるようになり,青春時代に形作られたと勝手に思っていたアイデンティティなど吹き飛んで,私はただの一介の Digital Labor に成り果てていた。0 か 1 の Digital Labor。
そんなとき心身ともに壊れて入院。医者から物珍しげな口調で「テーベーですね」の診断。肺結核。で,武蔵小杉の病院から東京都瀬田にある結核病棟に隔離されてしまった。長期欠勤のおかげで給料がゴミのような基本給しか出ないばかりか,保険やら何やらの諸処の天引きでマイナスとなり,逆に不足分を直ちに振り込めと会社の経理部から妻が催促される。会社というものに憎悪を覚えた。否,こんな事態でもきっちり源泉徴収しやがる国・自治体に心の底から憎悪を覚えた。この十年間はいったい何だったのか?
こんな古風な伝染病にやられたからには,当分娑婆には出られないと覚悟した。また文学書を手に取るようになった。ふたたびロシア語の頁を繰るようになった。病床にノート PC を持ち込んで,ロシア語を扱うプログラミングを試みるようになった。ダンテの『神曲』を,今度は寿岳文章による新しい訳で読むことになった。
ひとの世の旅路のなかば,ふと気がつくと,私はますぐな道を見失い,暗い森に迷いこんでいた。
集英社,1987 年,9 頁。
この冒頭は,西暦 1300 年というジュビレオの年,ダンテ三十五歳の境遇を表すとされている。「ほぼいまの俺と同じ歳」— 当時の私はそう考えてしまった。ダンテは終末の時が近づくのをひしひしと感じる時代背景のなかで「ますぐな道」を見失っている己にはっと気がつく。いまやこの作品の象徴は他人事ではないと私は惹き付けられたのである。もちろん,私自身は世の中の流れに身を任せていたに過ぎず,「ますぐな道」を見失ったなどという自覚なんてこれっぱかしもなかったんだけど。
村松は『神曲』のドラマの枠組みの照準を,ダンテ三十五歳の年ではなく,ジュビレオの年であるということに合わせている。これはある意味で正しい。でも,三十五というのは男が成熟するとともに人生の重大な岐路に立たされる年齢であってみれば,二十世紀の終わりをほぼ同じ歳で迎える私には,抜き差しならない状況設定だと思われた。
アーロン・グレーヴィチは『中世文化のカテゴリー』において,次のように指摘している。
〔中世においては:私注〕理想的な年齢とは三十五歳であった。これはキリストが「自分の地上の生を終えようと望まれた」年齢であった(これと関連したことであるが,当時のヨーロッパ人口の大半の平均年齢は研究者たちによって三十五歳であったと考えられている)[ 文献参照略 ]。ダンテは古代や中世の権威の説に従って,青年時代は二十五歳まで続き,成熟期は四十五歳で完了し,その後は老年期が始まると主張した [ 文献参照略 ]。
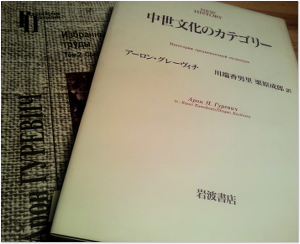
アーロン・グレーヴィチ『中世文化のカテゴリー』
さて。ダンテの『神曲』を手に取る読者は,お伽話を聴く子供のような素直な心持ちで読んでいるとすれば,主人公の地獄・煉獄・天国巡りの過程で様々な絵を見せつけられながら,誰しも,「俺ならどこに行く運命なのか」と考えてしまうのではなかろうか。と,思う間もなく,地獄の入り口すぐのところで,次のくだりに出くわす。
頭を十重二十重に錯乱させた私は言う。「師よ,耳に聞こえてくるこの物音は何?
苦しさに耐えかねているらしいこれら群衆は誰?」
答えて,師は私に。「これこそ,恥もなく,誉もなく,凡々と世に生きた者たちの,
情けない魂のみじめな姿。
神に逆らいもせず,さればとて忠順でもなく,ただ傍観していた天使たちの,
卑劣な一隊もかれらにまじっている。
もろもろの天はかれらを追放する。天の美しさがそこなわれないために。そして
底深い地獄もかれらを受け入れぬ。邪悪の輩と比べてかれらが自負しないために。」
私は言う。「師よ,何に苦しめられてか,かれらはこうまでいたく嘆く?」答えて,
師。「手短にそのわけを君に話そう。
これらの者は,死のうにも死ねない。またその盲目の生は,いといやしいゆえに,
他の身の上がみなうらやまれてならぬ。
かれらの聞こえが残ることを,この世は許さぬ。慈悲も正義もかれらをさげすむ。
われらも亦,かれらのことは口に上すまい。ただ見て過ぎよ。」

mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
どうも俺の落とされるのはここのようである — 病床にあって仕事も出来ないばかりか家族を泣かせていた己の卑小さに打ちのめされていた私は,直感的にそのように想像したものである。だって,これこそがフツーのパンピー・一般人ではなかろうか。己の不甲斐ない境遇ゆえに悪意をもって世を眺めていないか? そう,「恥もなく,誉もなく,凡々と世に生きた者たち」。「底深い地獄」にすら受け入れられない,要するに,蔑まれる,どうでもよい「いといやしい」者たち。「ただ見て過ぎよ」とは,堪える酷ないい草である。
これに続いて,ホメーロス,オヴィディウス,ホラティウスなどの,キリスト教徒でない古代の偉人たち(そこには導師であるヴェルギリウスも加えられるべき,もっとも尊敬すべき古代の藝術家たち)が,地獄の入り口すぐのリンボ(辺獄)に落とされているのを見る。洗礼を受けずに死した子供たちもそこにいる。「恥もなく,誉もなく,凡々と世に生きた者たち」と比べると,罪としてはより重く深いとされているのだが,しかも彼らとすぐ隣り合わせにいるにもかかわらず,決定的に違う敬意に満ちた扱いである。罪の重さと尊敬・軽蔑の念とは,どうやら,西欧の(中世の)人々にとっては別物のようである。
『神曲』を再読して面白いと思ったのは地獄・煉獄・天国巡りの順番・シーケンスである。地獄をどんどん降りて行くに従って出会う者たちの罪が深く極悪になり,ヴェルギリウスとダンテが地獄の最深部の魔王ルチフェルの胴体を伝うところで重力が逆転し,一転して煉獄を「上り」はじめる。ここで,なぜ地獄のいちばん深い,罪の極みの場所が煉獄の最下層との境目なのか。私はどうも理解できなかった。常識的には地獄の罪の浅いところが煉獄の下層との境界のように思われたからである。そのほうが罪の軽重の連続する空間のグラデーションとして自然ではないか。
しかし,こういう地獄・煉獄の構造のおかげで,主人公が日常の地点から地獄の奈落の底に急激に落ちてゆき,そこから今度は反転して煉獄・天国へと急激に上昇してゆくダイナミックな構成が得られたのである。まるでジェットコースターで底の見えない気の遠くなる長大なレールを急降下し下方向のGに押しつぶされそうになったあと,今度は急激に上方へ跳ね上げられその真逆のGに胸が張り裂けそうになる,そういう感覚である。ダンテが始終感覚を失って卒倒し,子供のようにヴェルギリウスにしがみついている道行きの姿は,まさにジェットコースターに乗る人の「うわーーー」と叫び続けるのと同じ陶酔に見える。
この辺りの不思議な感覚を,松村はまったく共有してはいないようだった。この感覚を巡って,中世人の内在論理を見事に説明してくれたのは,その後巡り会ったアーロン・グレーヴィチの本だった。彼は次のように述べ,中世人のクロノトポス(時空間)における時間・空間のダイナミックな同一次元的認識を鋭く指摘した。
中世における表象の二元論的性格のために,世界は両極に分かれて対立するものの組み合わせにはっきりと分割されたが,この二元論はまたたがいに対立するこれらのカテゴリーを垂直の軸にそってまとめあげていたのである — 天上的なるものは地上的なるものと,神は地獄の主たる悪魔と対置され,上という概念は気高さ,純粋,善という概念と結びつけられ,他方,下という概念は下劣,粗野,不浄,悪というニュアンスを持つ。物質と精神,肉体と魂という対比もその内に上と下というアンチテーゼを内包している。空間的概念は宗教的・道徳的なるものと分ち難く結びついている。天使が天から降りまた昇る夢をヤコブは見たが,このようなモチーフは中世的空間の基本的特徴である。この上昇・下降の観念を驚くべき力で描いているのがダンテである。物質と悪が地獄の下層部に集中させられ,精神と善が天国の高みを飾っているあの世の構造だけでなく,『神曲』に描かれているすべての動きが垂直化されている。地獄の深淵の絶壁や裂け目,罪業の重みによって引かれて起きる肉体の落下,身ぶりと眼差し,そしてダンテの用いる語彙自体 — これらすべてが《上》と《下》のカテゴリー,高尚なるものから卑しいものへの一方の極から他方の極への移行と注意を引きつける。
だがおそらく,最も力強く中世的時間認識を表現したのはダンテである。人間のはかない現世の「時」と永遠の対比,前者から後者への上昇 — これが『神曲』の「空間的・時間的連続体」のあり方を決定している。人類の全歴史が『神曲』の中で共時的に現存している。時は止まり,そのすべて,現在,過去,未来は同時性の内にある。


