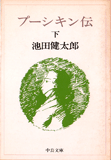英国映画『オネーギンの恋文』をとうとう観た。プーシキン生誕 200 年に当たる 1999 年,マーサ・ファインズ監督作品。主演は,レイフ・ファインズ,リヴ・タイラー。レイフ・ファインズはプーシキンの大ファンなのだそうである。あの英国風のシニズムと情熱の入り混じった風情は,オネーギン役として悪くなかった。
名作とされる文学作品に基づく映画に,私はたいていがっかりさせられて来た。だから,私のもっとも愛読する古典のひとつである『エヴゲーニイ・オネーギン』の映画化を目にするのは,自分の作品イメージが壊されるのではないかという怖れのほうが期待を遥かに上回ってしまい,私はこの映画をこれまで敬遠していたのである。果たして,ある意味でこの Onegin も,原作の恋愛小説としての側面に主な焦点を当てた一面性を拭い切れなかった。
しかし。麗しのリヴ・タイラー! よくぞタチヤーナ役に選んでくれた。私はただそれだけでこの映画に感謝しているんである。オネーギンとタチヤーナがはじめて出会うシーン。タチヤーナが扉の奥からオネーギンをそっと覗見する。オネーギンはそれに気付かない振りをしている。そのときのタチヤーナ=リヴ・タイラーの謎めいた凝視だけで,私はこの映画に満足した。
田舎育ちでフランス小説的世界に憧れるタチヤーナは,首都ペテルブルクから来たオネーギンに一目惚れし,うぶな心のまにまに恋文を書く。ところがオネーギンは心を動かされながらもその求愛をにべもなく拒絶する。些細な諍いから詩人レンスキイを決闘で殺したオネーギンは旅に出る。久方ぶりにペテルブルクに舞い戻って来たオネーギンは,社交界の貴婦人に変貌したタチヤーナと再会し,今度は彼が恋心に狂って彼女に恋文を認める。ところがタチヤーナは運命に従い夫への貞節を守ると断言し,オネーギンの愛を退ける。
おおまかな「筋」はこのようなものである。ところで,こんな筋書きを面白いと思うだろうか? 正直「面白くない」という反応が多いのではないだろうか。チャイコフスキイによる同作品に基づくオペラを観て,「なんとオネーギンは身勝手でイヤな奴なんだろう! そんな奴に『今も愛してます』なんて言うタチヤーナも理解不能!」という意見を,私は耳にしたことがある。
たしかに,チャイコフスキイのオペラでは — 極めて通俗的なことに — 田舎娘が美貌の貴婦人に変貌したところにオネーギンの心変わりの理由が読み取れるようになっている。しかし,こういうオネーギンの人物像に対する不満は,思うに,作品における「ストーリー」の意味合いがそもそも難解であるということと,プーシキンの原作そのものをきちんと読んでいないということとから,出て来るのである。
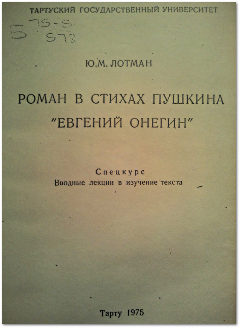
Ю. М. Лотман -
Роман в стихах Пушкина
«Евгений Онегин», Тарту 1975.
主人公の振る舞いはどうも納得できないという感想は発表当時から出されていて,古来,作品の「ストーリー」の論理について多くの研究者が様々な解釈を与えて来た。そのなかで,ユーリイ・ロートマンは「作品の筋は起こらない事件で組み立てられている」と,面白いことを書いている(Лотман Ю. М. «Роман в стихах Пушкина “Евгений Онегин”. Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста» Тарту 1975. с. 75.『プーシキンの韻文小説「エヴゲーニイ・オネーギン」— 特別講義 テクスト研究入門』,太字部は原典強調)。つまり,作品の筋は小説として想定される恋愛遊戯を唆しながら読者の期待をはぐらかすように進む,というのである。
恋物語というものは,普通,求め合う男女が障碍を乗り越えて結ばれる,ないしは障碍のために別離で終わる — そこにこそ読者の興味を惹き付ける「ストーリー」性がある。ところが『エヴゲーニイ・オネーギン』にはその障碍がまったくない。オネーギンはペテルブルクで放蕩三昧をした洒落者である。そんな男に,タチヤーナは自分から恋文を書く — これは当時の貴族社会では嫁入前の処女の振る舞いとしてあってはならない不道徳だったが,その倫理という障碍を乗り越えてオネーギンが愛を受け容れるかと思いきや,「そんなことをすると破滅しますよ」と,しごく常識に則って「立派に」タチヤーナを拒絶する。そもそも,タチヤーナの親はオネーギンこそ娘の婿だと期待しているくらいである。二人が結ばれるのにはなんの障碍もない。同様に,当時の貴族女性は,結婚してしまうと情夫と密通しようが夫に見咎められない限り比較的自由だったのであってみれば,オネーギンとの「不貞」にはじつはなんの障碍もない。なのに愛は成就しない。
はぐらかし,と言われても宜なるかなというところだろう。おまけに,恋愛遊戯がいつ起こってもおかしくないくらい,詩行にはエロティックな仄めかし,猥褻表現が満載なのである(日本語訳ではほとんどわからないのだが)。
ロートマンは,プーシキンが文学臭さを作品の至る所に振りまきながら,こういう「ストーリーの不在」を強調したことにこそ,レアリズムの新機軸を認めている。現実はそんな小説的じゃないよ,というわけだ。語り手はこの作品が作り物であることを堂々と書きさえしている(「詩の構想や主人公の名は/もう考えてある。/これでどうやらこの小説の/第一章は書きおえたぞ」木村彰一訳,講談社文芸文庫,61 頁)。
オネーギンの人物像についても,原作では,タチヤーナは — フランス小説の色眼鏡に捕われて — 彼が「救世主」なのか「誘惑者」なのか,「天使」なのか「悪魔」なのか,ことあるごとに判じようとするが,筋の運びで裏切られそのいずれでもないことが判明する。最後にタチヤーナは彼を「チャイルド・ハロルドのパロディー」と断ずるわけだが,こうした人間の「本当の」姿は何かという問いがはぐらかされることは,それがすなわち矛盾に満ちた人間のあり方を示している。「本当は」いい/悪い人なんだ — こういうことでカタルシスを覚える現実的人物評価は幼稚だというのだ。現実は小説とは異なり,もっと多面的だというのである。
ここには「現実」と「小説」との乖離に対する諧謔がある。一方で,それでも — その諧謔ゆえに「虚構」であることが強調されているにもかかわらず — 人間感情の真実が光っている。それは,人を恋してしまうのには理由がない,ということである。オネーギンが貴婦人タチヤーナに狂うのは,恋してしまったから,ただそれだけであって,そこには「ストーリー」などなくてよい。かつて賢者風の教訓を垂れて愛を拒んだことなど,いまこの時の思いとはなんの関係もない(そういう意味では確かに「身勝手」かも知れない)。恋愛物語としての『エヴゲーニイ・オネーギン』の真実は,ただその一点につきると私は思う。二人がそれぞれ相手に対して恋心を燃やす描写には,いずれにも「子供のように」とある。つまり,人間の沸き立つような心に,「理由」なんて小賢しいものはないということなのである。
「ストーリー」などないなんて,それで小説といえるのか,という理屈を言う人があるかも知れない。これは散文小説ではなく「詩」(「韻文小説」)なのである。映画の一瞬一瞬,場面の結構そのものに心をときめかすように,詩の一句一句,一節一節そのもの,そしてその総合こそが魅力なのである。『エヴゲーニイ・オネーギン』の「小説」としての構造の複雑さ,現代小説にも珍しいインテリジェンス,作品の豊かさは,まさにここにある。
『エヴゲーニイ・オネーギン』はプーシキンの「創作日記」的作品である。先行きを見切ることなく書きはじめられ,インテンシブに仕事をするプーシキンには珍しく「7 年と 4 ヶ月」の長い期間に亘って書き続けられ,その時々の詩人の関心事が反映されている。なのに,決闘(と,映画には描かれていないタチヤーナの夢)を軸にして,オネーギンとタチヤーナの告白,恋文のやりとり,主人公の心情の動きがシンメトリカルに配置され,独特の統一感がある。この天才の端倪すべからざる構成の妙である。
この映画には,ヴォルコンスキイ令嬢が登場する。嫁き遅れたオールドミス,オネーギンに仄かな恋心を抱いているが,オネーギンからは一顧だにされない哀しいブス・キャラとして。原作にはないエピソードである。
ヴォルコンスキイ公爵夫人(女性なんで,ロシア風にはヴォルコンスカヤ公爵夫人)は実在した美しい女性で,プーシキンの親しい人だった。しかしながら,実際のヴォルコンスキイ公爵夫人は,1825 年のデカブリスト蜂起に連座して流刑となった夫に付き添って,シベリアに行くことを選んだ悲劇の貴婦人である。原作の最後の詩句「冒頭の連を/私が読んできかせた者たち......[...]/そのある者はすでに亡く ある者は遠方にいる」(同書 385 頁)にある,「遠方にいる」ある者たちのひとりである。
映画では,なぜ彼女の名がこのような滑稽なシチュエーションに組込まれてしまったのか,私はいま少し考えているところである。プーシキンの伝記は,詩人が可愛い女と思うやのべつまくなしにその尻を追いかけ,嫉妬に狂い,放蕩と決闘沙汰に明け暮れた逸話で満ち満ちていて,その冷静な作品世界との相互関係に私などはくらくらしてしまう。詩人が,気のない女から愛される立場に立つとき,手ひどくその女性の心を傷つけた話も伝えられている。ヴォルコンスキイ公爵夫人の哀れな挿入は,そういう恋多きプーシキンの冷たい側面もろとも受入れようとするレイフ・ファインズの心意気なのかも知れない。
プーシキンの伝記は好色一代男のロマンといってよい。日本人は池田健太郎先生による素晴らしいプーシキン伝を読むことができる。私は高校生のころこれを読み,プーシキンに夢中になった。もう絶版になってしまったのが残念だが,まだ入手できる古書でぜひお読みください。
![オネーギンの恋文 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41c%2BXtDoiCL._SL160_.jpg)