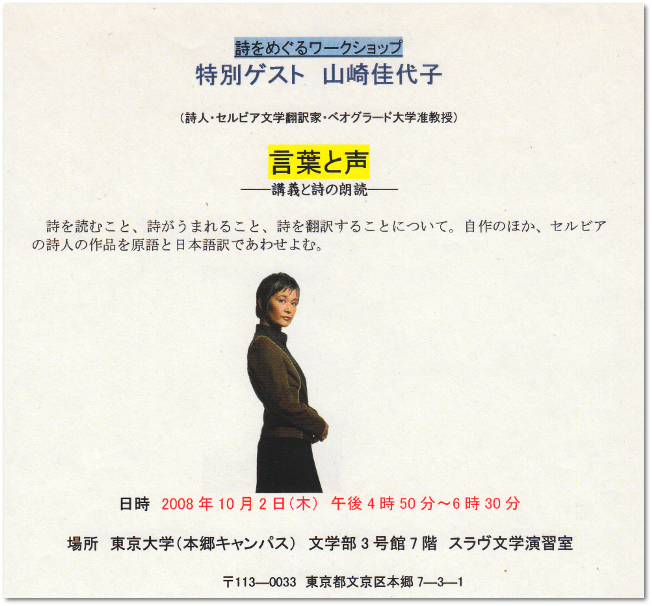
10 月 2 日夕方,セルビア・ベオグラード在住の詩人・山崎佳代子さんを迎えた『詩をめぐるワークショップ』というイベントに参加してきた。これは東京大学文学部現代文芸論・スラヴ語スラヴ文学研究室が共催したもので,東大本郷キャンパス文学部三号館で開かれた。私は東大のホームページでこの催しを見つけ,仕事に都合をつけて会社を抜け出し,聴講させてもらうことにしたのである。会社勤めでも,たまにはこういう経験がないと乾涸びてしまう。
狭いスラヴ語スラヴ文学演習室に 4,50 人の学生,先生が集まっていた。どうも会社員は私ひとりのようで,スーツ,ネクタイ姿は私だけ。さぞかし浮いて見えたのではないだろうか。直前に部屋に入った私は山崎さんのすぐ側,N 教授の隣の席に座ることになってしまった。ロシア書籍のあの懐かしい臭い。
山崎さんの講義,セルビア詩人ヴォイスラフ・カラノヴィッチと山崎さん自身の詩の朗読,参加者同士での討論,山崎さんの質疑応答という内容だった。
近年の便利な都会生活,グローバリゼーションで生活プロセス(もっと広く,国家,ジェンダー等の身体感覚そのもの)が失なわれつつあるのではないか。人が声を出す,それに聴き入るということの意味が失われているのではないか。彼女の日本語・セルビア語二カ国語詩人としての詩への思い — それはセルビア語で詩を書くとき文法,語法など外国語であるがゆえの緊張感・怖れを強いられるが,しかし慣れた日本語でも本質は同じ。散文は先へ先へ進もうとする。詩は同じ場所を徘徊し眺め回す。散文は外側から出てくる。詩は内側から湧いてくるのを待つしかない。スラヴの人にとって,魂の揺さぶりを伴わないものは知識とはいえない。
山崎さんのこんなお話で,人間の発する言葉のただならなさ(どうも私にはうまく言えません)に私は動かされた。言葉が知識と結びつく必須の過程に「魂の揺さぶり」を見出すところがホンモノの証。
これからの詩の言葉は
林檎の皮に書こう
...
鉛筆はいらない するどいナイフも
紙の白い皮も
意味のむこうの梢に
さしのべる手もいらない
...
山崎さんは NATO によるセルビア空爆のころ,死に直面した緊迫感のなかで詩(詩集『薔薇,見知らぬ国』)を書き,原稿が成るそのつど日本の書肆にファクシミリを送ったそうである。セルビアはコソボ紛争で西側諸国のメディアによって民族浄化の悪の権化のように扱われていた。それは 1999 年当時も今も変わらない。西欧のメディアに対してまったく無批判な日本のマスコミも,なんの疑問もなくその尻馬に乗り続けている。『薔薇,見知らぬ国』から,痛い詩を二篇だけ。
黒い国
この指が
あなたの髪にとどかない
空の深みに
鉛が流しこまれ
薔薇のめざめた庭は
見知らぬ土地になっていく
橋から人が消され
水に虹はまだ見えない
花冷え
冷たい雨に
窓を閉ざしても
ぼくの声を感じるね
長い列をくみ
人々は過ぎてゆき
川はせせらぎ
闇のなかで
はなみずきが香った
きみはぼくの音楽……
山崎さんは,調べてみたら,なんと私の大学の露文科の先輩。気さくで美しいひとであった。
