どういうわけか『うたかたの記』を読んで,そのロマンに胸がきゅんとなった。ルウドウヰヒ狂王を錯乱させ湖に溺死したマリィ。なんとロマンチックな物語か。という次第で,ここのところ森鷗外を再読していた。正直なところ,いままで,鷗外がこんなに易しく直にして感動的な物語作者だったとは思わなかった。
鷗外といえばわが国近代文学の泰斗であり,好きとか嫌いを超越した古典的大作家の領域に鎮座している。しかしこの現代にあって「好きな作家は?」と聞かれて「森鷗外です」と答える本好きがどれだけいるだろうか。私などは逆にその問いに彼の名をあげる人に出くわすと,まず「ブランド指向の似非読者」だと思ってしまうくらいであった(私の知る人物で,そう答えたのはことごとくイヤミな野郎であった)。いまの真面目な読書子なら,漢文の白文や原語綴りの外国語がそのまま挿入される鷗外の文体に衒学の嫌みを覚えるのが,正当な反応であろう。鷗外における漢文訓読体と伝統的雅文調・西欧的翻訳調との融合の試みには,明治新時代の文体創造の試練・苦難があったのだが,古典的教養と様式感覚とを失った現代人は,もはやそこに「衒学」しか読み取れなくなってしまった。この現代にあって鷗外より現代的でかつ面白い作家は海外にも,国内にもゴマンといるのになんでいまさら鷗外なの? 鷗外は事実その作品よりも,文学博士にして軍医総監まで上りつめた明治のエリート中のエリート,権威ある最高級の教養人とのイメージが燦然と輝いているといえよう。鷗外を愛読するということで「教養人」の雰囲気を身につけた気分になるではないか! つまり,無教養な現代人には,鷗外はもはや理解されなくなってしまったということなのである。
私も高校生のころ『高瀬舟』,『舞姫』などを読み,漢籍の伝統に立ちつつ西欧文学の豊かなレミニサンス(陰陽の影響)に満ちた硬質の文体に虞れをなした口である。文学とは難しいものだと。「偉い先生のご著書」というわけで有り難がって読んだものである。そんなものだから,「好きな作家は鷗外だ」などと外に向かって言うことは,畏れ多くて憚られるだけでなく,なにか後ろめたい気取りなしにはできそうにないのだった。そうして,鷗外を読む本当の楽しみを知らずに学校を出てしまった。
皮肉なことに,私は社会人になってはじめて,本を読むということに,特別の目的も,ましてや教条主義もなく,たんなる面白さばかりを求めるようになって,先入観なしに他人の文章を読み解くことの楽しさを知ったように思う。面白そうが動機であり,面白いかそうでないかが結果になった。今回『うたかたの記』にはじまり『阿部一族』,『山椒大夫』,『文づかひ』,『ヰタ・セクスアリス』,『寒山拾得』などなど鷗外の作品を読み返してみて,私の鷗外が「偉い先生」から「本当に面白い物語をしてくれる作家」に変わったのである。
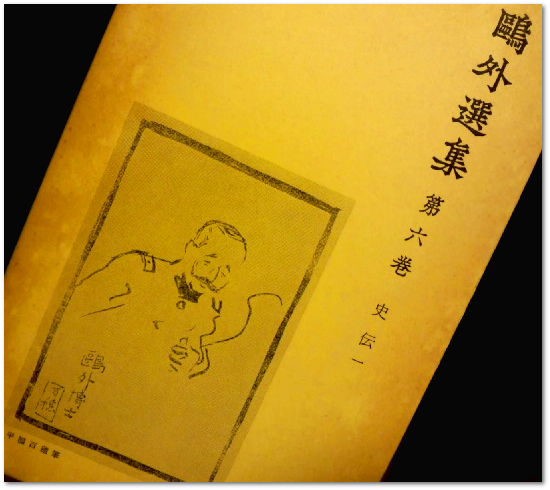
『鷗外選集』第六巻史伝,岩波書店,昭和 54 年
じつは『渋江抽斎』を,私は今回の鷗外渉猟でやっと読み通すことができた。この作品を昔,岩波鷗外選集第六巻(1979 年刊)— 新書版・クロス装の二段組・旧字旧仮名遣いの上製版で読みはじめたが,人物の名と出自からなる途方もない大海を,故事に由来する難解な漢語,白文のままの漢詩文が滔々と流れ行くかのような文勢に,注釈という羅針盤なしでは付いて行かれなくなってしまい,途中で投げ出してしまったのだった。岩波鷗外選集は注を付さず,準備のない読者のためにはまったく不親切な作品集であった。今回,尾形仂による詳細な注釈を掲載した中公文庫版を手に入れた。漢文も読み下し文に書き換えられ,ルビを振られ,意味が明らかになった。注釈により難語もいまや明快である。なにも難しいところがなくなった。仮名遣いなどの表記は別としても,新潮や中央公論から出るいまの普及版は必ずこうした利便を慮っている。古い作家の読み物はこういう文庫本で読むほうが絶対によい。
さて『渋江抽斎』。これは鷗外の歴史的関心に基づく文藝作法の最終形態と評されている。岩波鷗外選集では「史伝」の類に加えられている。読んでみるとなんのことはない「伝記」である。「主人公」抽斎は医師であり漢詩文をよくし,愛書家,芝居の通人であり,勤王派にしてかつ洋学受容に開かれた人士であって,鷗外と同じくするその性格から作者の自伝的教養小説のような読み方をされている。
この作品の面白いところは,思うに,まさに人物の名と出自からなる途方もない大海であるところである。
斉民は小字を銀之助という。文化十一年七月二十九日に生まれた。母はお八重の方である。十四年七月二十二日に,御台所の養子にせられ,九月十八日に津山の松平家に婿入りし,十二月三日に松平邸に往った。四歳の婿君である。文政二年正月二十八日には新居落成してそれに移った。七年三月二十八日には十一歳で元服して,従四位上侍従参河守斉民となった。九年十二月には十三歳で少将にせられた。
このように,ある人物が言及されるとその字(あざな),出自,役職の変遷,などなどが細やかに羅列される。人物に関心のない者には退屈極まりないのではなかろうか。その合間に彼のエピソードが挿入され,物語としての肉付けが成っているといってもよい。このスタイルは一貫していて,これこそ「史伝」の特徴になっているといえそうである。
私が面白いと思うのはこのスタイルそのものである。それほど有名でもない付随的な作中人物について,かくも事細かな事項を「羅列」されるとウンザリするほうが普通かも知れない。しかし考えてみると,自分の関心のある領域についてなにかの記録を読むとすると,その属性の細部が書かれていないとわれわれは満足しない。たとえば,モータースポーツのファンならば,あるグランプリの記録を読むとき,「1976 年の F1 ドイツグランプリでフェラーリは大事故を起こした」という記述だけでは納得しない。「1976 年の F1 ドイツグランプリでフェラーリは大事故を起こした。サーキットはニュルブルクリンク北コース全長 20.8 キロ。マシンはフェラーリ・モデル 312T2,ボクサー・エンジンと称された排気量 3,000cc 12気筒水平対向エンジン搭載。ドライバーはオーストリアのニキ・ラウダであった」のように,門外漢にはどうでもよい型式やスペックが書かれていないと読む理由がないのだ。これでも不足を覚えるオタクが当然いる。そのときのカーナンバーは? ラウダの当時の年齢は? ドイツグランプリの 312T2 仕様の特徴は?
鷗外の歴史小説に登場する人士の属性のあの大名行列は,まさにこの精神なのである。もうその列挙そのものが詩的効力を発散する。もちろん,その事蹟を愛する者だけに通用する詩である。「列挙の詩学」とでもいうのか。『阿部一族』で切腹殉死した武士についてひとりひとりその名前,出自,俸碌などなどを記述することが小説の藝術的結構においてどのような有効性があるのか,はなはだ疑問に思ってしまう。けれども,作者と,語られる事蹟を神聖視・酷愛する者とにとっては,それでよいのだ。聖書の冒頭・マタイ伝福音書第一章第一節を見るがよい。イエス・キリストの延々たる系譜である —「アブラハム,イサクを生み,イサク,ヤコブを生み,ヤコブ,ユダとその兄弟らとを生み,...」(『新約聖書 詩篇付 改譯〔文語訳〕』日本聖書協会,2007 年,p. 1)。これも名前の列挙だけでこと足りる精神の現れであろう。しかし,「詩」とはまさにそういうものではなかろうか?
もうひとつ『渋江抽斎』の面白いのは「主人公」抽斎が物語のほぼ半ばで亡くなってしまう点である。「抽斎歿後第三年は文久元年である」型のマイルストーンとともに,抽斎の係累のエピソードが後半を占めているのである。妻・五百(いお),子息・保さん,優善さんなどの,抽斎に比べると「普通」の人たちの事蹟が生き生きとしている。五百が,抽斎を騙そうとする夜盗を半裸で怖気付かせて撃退したというくだりはじつに痛快である。これは,じつは抽斎にかこつけて時代の人々,世代の姿を描いた「反伝記」なのではなかろうかと思われるくらいである。安寿と図師王の物語なのにそのアンチテーゼの登場人物『山椒大夫』をタイトルにしてしまう一種独特の韜晦が,ここにもあるように思う。
鷗外の文学には,弱さを自覚した者の静かなる精神的抵抗,弱さを成り立たせたことどもへの限りない愛情がある,と私には思われる。ここにこそ現代人を感動させる核心があるというのが私の持論である。そこには明治のエリート,「偉大なる教養人・大先生」としての気取りや尊大や自信満々や自己肯定などは微塵もないのだ。「わたくしの杯は大きくはございません。それでもわたくしはわたくしの杯で戴きます」(『杯』,『山椒大夫・高瀬舟』新潮文庫版所収,1979 年,p. 13)。『舞姫』,『うたかたの記』,『文づかひ』のいわゆるドイツ土産三部作は,その雅文体の文体効果がいかなるものであれ,西洋人のようになりたくてなれなかった疎外感・敗北の物語である。『ヰタ・セクスアリス』の主人公・金井は自分の容貌に自信がないがゆえに恋愛の「美しい夢」を見ることができない,まさにコンプレックスに囚われた弱き者である。しかし,「... 僕は陽に屈服して陰に反抗するという態度になった。兵家 Clausewits は受動的抵抗を弱国の応に取るべき手段だと云って居る。僕は先天的失恋者で,そして境遇上の弱者であった」(『ヰタ・セクスアリス』新潮文庫版, p. 35)とある。こういう文章に見られるとおり,その弱さは西欧的視点によって立つものであって,鷗外は日本(や中国漢詩文)の伝統・歩んで来た道程を無条件に愛することによって「陰に反抗」するのを己の生き方だと見たのかも知れない。『渋江抽斎』はその陰なる受動的抵抗の静かな凱旋である。




